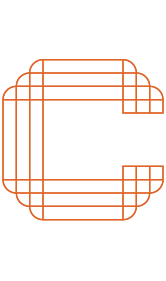アメリカで博士課程の学生をしているときに、アメリカ永住権、通称グリーンカードの申請をしました。センシティブな情報なので細かいところまでは公開できませんが、アメリカ留学、就職の悩みで一番相談されるトピックなので、書ける範囲で試しにまとめてみます。アメリカ政府に目を付けられるまでの期間限定です。
グリーンカードを取ることをすべての人に勧める気は一切ないし、境遇が違えば同じような手段を取れない場合もあるし、今後アメリカの方針が変わる可能性も大いに考えられるので、あくまでも個人の体験談として読んでください。
意外と簡単なプロセスだからとりあえず申請してみようと思えるかもしれないし、永住権のデメリットを知って申請するのをやめるという決断をするかもしれないし、この記事の受け取り方はもちろん自由です。この情報を公開する意図は、どんな結論になるにせよ、現実的な選択肢の一つとして永住権を検討するきっかけを提供することです。
はじめに
グリーンカードには複数のカテゴリーがあります。例えば、抽選や結婚も永住権取得の手段の一つに含まれます。
準備する書類はカテゴリーにより大きく異なりますが、この記事は、その中でもアメリカでの雇用に基づくカテゴリー、EB(Employment-Based)の中の、EB-2についてです。最新の情報はUSCISで確認してください。
- EB-1:卓越した能力を持つ人材
- EB-2:高学歴専門職・特別な能力を持つ人材
- EB-3:熟練労働者・専門職・その他労働者
- EB-4:特殊移民
- EB-5:投資家
私のようにアメリカの大学の博士課程に在籍中に申請する場合、EB-2が最もメジャーな気がします。永住権取得後は、アメリカ市民権に近い権利が認められ、それに伴う責任が生じます。詳細はこれもUSCISでチェックしてください。選挙権は貰えません。グリーンカードからその後市民権を取っても大統領にはなれません。
よく知られている通り、代表的な取得のメリットは、アメリカで永続的に就労する権利を得られること、それに伴って卒業後の就職先の選択肢が広がることです。特にアメリカの航空宇宙業界においては、雇用条件として特定の在留資格を求めるポジションも多く、永住権を保持していることがキャリアに有利に働くケースもそれなりにあります。例えば、以前の職場のNASA-JPLでは、グリーンカードがなくても就職は可能なものの、その有無によって携われるプロジェクトの種類に差があったりしました。
申請に必要なスペック
EB-2でグリーンカードを申請する場合、高学歴・特別な能力とは、基本的には研究能力のことを指します。それを測るわかりやすい指標として、USCISは、取得した学位、論文が掲載されたジャーナルの権威や引用数、査読を担当したジャーナルの件数などを審査の際に考慮します。特に査読数は意外と大事なファクターのようなので、グリーンカードを見据えている人は意識的に依頼を引き受けた方が良いと思います。他にも、政府直属の研究機関と共同研究経験があったりすると良かったりもするみたいです。
- 取得学位:M.S. in Space Engineering・California Institute of Technology&学士・京大
- 論文引用数:たぶん60ぐらい
- 論文数:ジャーナル論文5・学会論文4
- 論文査読数:ジャーナル論文11・学会論文4
他にも、NASA-JPLと長く共同研究をしていたことは、もしかしたら政府直属の研究機関とのつながりとみなされたのかもしれません。ただ、実際のところ、申請時に必要なスペックは完全にケースバイケースで、申請者の携わる分野やバックグラウンドにより大きく異なるようです。という訳で、このスペックを参考にするよりも、自分のCVを弁護士に送って判断してもらうのが確実です。今のところ無料でやってもらえます(https://www.wegreened.com/Free-Evaluation)。どのカテゴリーで申請すべきかとかもある程度教えてくれます。
同じ弁護士事務所のブログ(https://www.wegreened.com/blog/)にも、さまざまなスペックでグリーンカードを申請した人たちが紹介されているので、自分に近いケースを探してみるのもいいと思います。 例えば、論文0、論文引用数0の体験談もあったような気がします。
申請のプロセス
必要な書類の中で少し手間がかかるのが推薦状です。グリーンカードの推薦状には、Inner CircleとOuter Circleという概念が存在して、前者はこれまで自分が関わったことのある組織、後者は一度も関わったことのない組織を指します。細かい定義については弁護士に確認してください。アメリカ大学院入試等の推薦状とは異なり、ここではOuter Circleからの推薦状が重視されます。つまり、私のことを個人的には知らず、学術成果を通じてのみ知っていて、かつ推してくれる人を探さなければなりません。
というととても大変に聞こえますが、推薦状の内容は比較的形式的なもので、書く側にとって執筆自体の労力はないに等しいです。したがって、学会で知り合った他大学の教授や、自分の論文を引用してくれた教授に、自分の指導教官をccして丁寧にお願いすると、快諾してくれる確率は高いはずです。私の場合は、推薦状を書いてくれそうな人が多い京大、Caltech、NASA-JPL、MITはInner Circleとみなされてしまったので、私の論文を引用してくれた論文を見漁って、最終的にはUIUC、Michigan、Stanfordの教授にお願いしました。
他にもさまざまな書類が必要ですが、そのほとんどは事務作業的に作成できるものなので、特に心配する必要はないと思います。お金にもし余裕があるなら、弁護士(https://www.wegreened.com/)にお願いするのが圧倒的に楽です。推薦状の下書きとか、推薦者の選定とか、必要な書類・推薦状の枚数の確認とか、その他諸々ややこしいタスクを一手に引き受けてくれます。仕事もびっくりするぐらい早いです。
申請から取得までどのくらいかかるかなどのふわっとした質問にも、現在のアメリカの状況の応じて、分かる範囲で一瞬で答えてくれます。
おわりに
申請前のビザのステータスによっては、グリーンカード申請中にアメリカから出国できなかったり、日本に一度帰国しなければならなかったり、就労が制限されたりする可能性があります。また、EB-2グリーンカードの申請には2つのプロセスがあり、それを別々に進めるか同時に進めるかによって、課される制約も変わってきます。
ということで、特にアメリカの情勢が刻一刻と変わりうる今は、この記事を含めネットや知り合いづての情報を鵜呑みにせず、まずは最新の情報に精通している弁護士に相談(https://www.wegreened.com/Free-Evaluation)することをおすすめします。実際にグリーンカードを取るか、お金を払ってサービスを受けるかどうかに関わらず、とりあえず気軽に査定してもらうと前に進みやすくなると思います。
ちなみに、制御理論・ロボティクスの分野でジャーナルの査読に興味がある方がいたらぜひ連絡してください。査読依頼送ります。